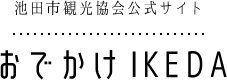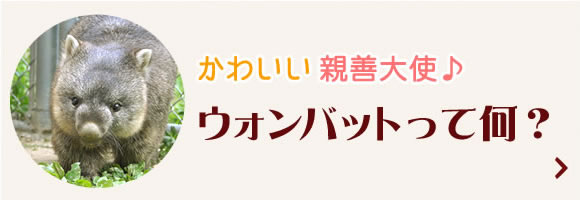五月山動物園

ウォンバットに会える♥入場料無料がうれしい動物園
五月山動物園は、五月山公園内にあり、池田市民を始めとして、近隣市町村から多くの人が訪れます。1957年(昭和32)の五月山動物園の開設以来、みなさんに親しまれています。
広さ約3,000平方メートルで、オーストラリアからやってきた珍しいウォンバットやワラビーなどのほか、アンデスの高地(標高4,000m以上)に住むアルパカも居り、見どころもいっぱいです。
他ではあまり見る事ができないウォンバットですが、生息地のオーストラリア以外での繁殖は殆ど例が無いのですが、五月山動物園では2世が誕生し、今も元気な姿を見せてくれています。




五月山動物園に、ご家族・お友達同士で是非一度お越し下さい。
きっと、のんびり・ゆっくりと一日をお楽しみ頂けます。
スポットDATA
| 所在地 | 池田市綾羽2丁目5-33 |
|---|---|
| 電話番号 | 072-753-2813 (五月山緑地管理センター) |
| 営業時間 | 午前9時15分~午後4時45分まで |
| 休園日 | 火曜日 (祝日の場合は直後の平日) |
| 駐車場 | 五月山公園駐車場など(有料) |
| 料金 | 無料 |
| 公式HP | http://www.satsukiyamazoo.com/ |